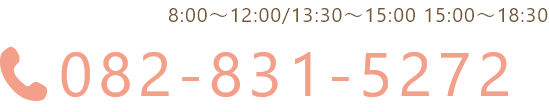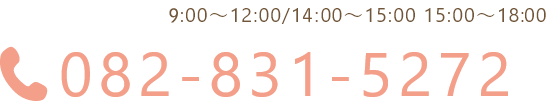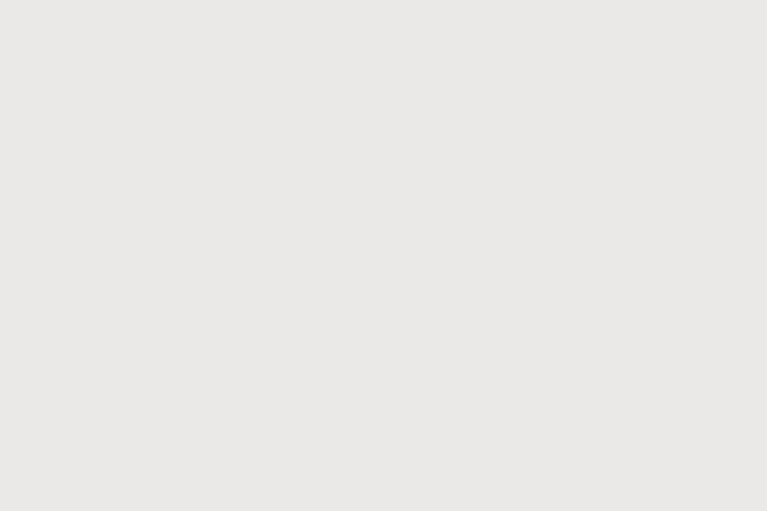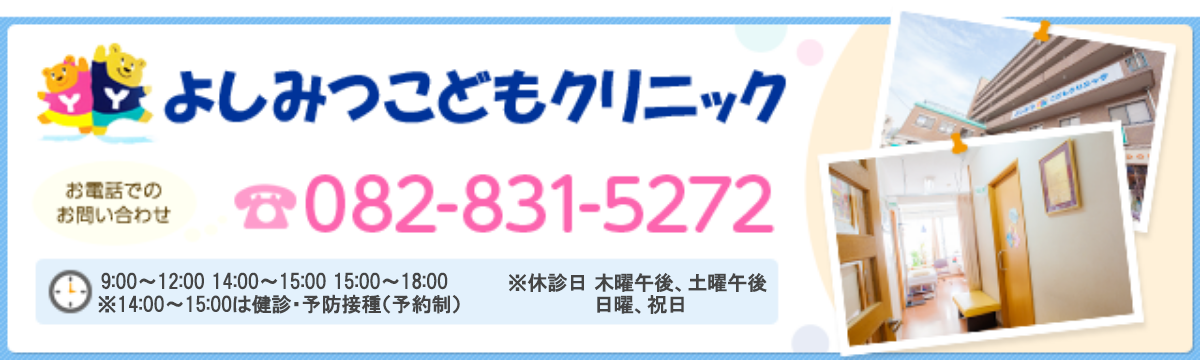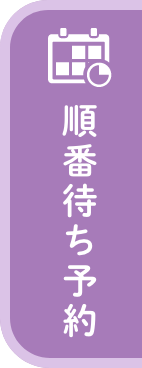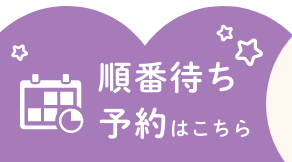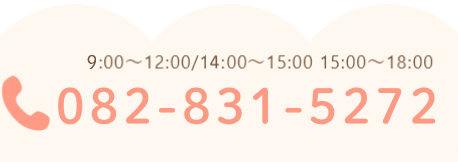最近の院内誌
今回は、温泉についてです。温泉は、温泉法(おんせんほう、昭和23年法律第125号)によって、限られた資源を守るために、掘削の許可、採取の許可、温泉の利用の許可に関して規定されています。温泉成分に関しては、水温が25℃以上、または特定成分について含有量が基準以上のものと定められています。その昔、温泉は、火で風呂を沸かさなくてもすんだので楽だったのでしょうね。たとえば、
単純温泉:由布院温泉(大分県)、道後温泉(愛媛県)
塩化物泉(海水の成分に似):城崎温泉(兵庫県)、指宿温泉(鹿児島県)
硫酸塩泉:玉造温泉(島根県)
二酸化炭素泉:有馬温泉(兵庫県)、別府温泉郷(大分県)
酸性泉:草津温泉(群馬県)
硫黄泉:草津温泉(群馬県)
雨や雪が地中にしみ込んで、火山地帯で地下、数㎞~10数㎞の部分が、マグマ溜まりであたためられたり、地下の高温岩帯や地熱によってあたためられたりして、断層から自然に湧き出したり、人工的なボーリングで掘り当てたりして、温泉になっています。
温泉の効果は、温泉の含有成分による効果と温熱効果があげられます。何より海洋・森林などの環境からのリラックス効果もあるのでしょうね。
ただ、温泉は、大腸菌数などチェックして衛生面には気を配られているのでしょうが、不特定多数の人が入浴しているのですから、自宅で哺乳瓶を消毒したり、口から入れるものに対して神経を使っているような乳幼児にはあまり好ましくないかもしれませんね。